本棚A - 6列目(1/2):妻に先立たれた夫の思いとインドの謎パワー、「ぢるぢる旅行記」と「インドぢる」
本棚6列目、ここも種類が多いので二分割でお送りします。

この本棚は棚の高さをそれぞれ約3cm間隔で調節できる仕様になっており、同じサイズの本をまとめて並べることで余分な空間(デッドスペース)を減らす工夫をしています。また、本棚の安定性を高めるため、小さく軽い本はなるべく上寄りに、大きく重い本は下寄りにと振り分けている関係で、ここから先はしばらくA5サイズ以上の漫画本の紹介が続くということになります。
では今回は、左端の「ドロヘドロ」から、真ん中少し先の「監督不行届」まで語ります。
「ドロヘドロ」林田 球(20巻~)
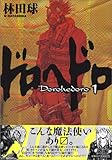
- 作者: 林田球
- 出版社/メーカー: 小学館
- 発売日: 2002/01
- メディア: コミック
- 購入: 13人 クリック: 89回
- この商品を含むブログ (132件) を見る
みんな大好きドロヘドロ、読めばたちまち引き込まれる、この不思議な世界観、グロいのにかわいい、切ないのにムキムキ、恋ではなく絆、いまだすべて混沌の中、はい、それが、ドロヘドロ。
私のこれまでの本棚語りをざっとお読みになられた方なら、この流れでドロヘドロが置かれているのは当然だと思われると思います。私はこういう、唯一無二の作風が大好物でですね、だってこの世にドロヘドロと似てる漫画なんかひとつもないじゃないですか、いや世界は広いからどこかには存在するのかもしれないですけど、私の知る限りドロヘドロはドロヘドロだけ、ジャンル分けすらできない、もはやドロヘドロというジャンル、それほどの独自性があり、しかも面白いしかわいい。最高の漫画です。
さてこの漫画、私が自力で「発掘」したわけではなくて、確か6巻くらいまでしか刊行されていない頃に、ヲタク友達から教えてもらって知りました。初めて1巻の冒頭を読んだときには、それまでまったく見たことのない絵柄に驚き、このまま読み進められるかどうか少々不安に思ったものです。ただそれは杞憂で、1巻を読み終わる頃には早くも世界観に魅了され、あっという間に心奪われてしまいました。すすめてくれた友人にはただただ感謝です。
その後、友人宅で大葉入りギョーザを作って食べるということもしました。実のところ大葉があまり好きではない私ですが、ギョーザにすると余裕で食べられました。マジ余裕でした。おいしかったです。ニカイドウのギョーザ、漫画世界に入ることができるなら一度は食べてみたい逸品ですね。あの世界に入ったら私みたいな軟弱者はすぐ死にそうですけども。
キャラクターで誰が好きかというと、みんなかわいいのでみんな好き、ということになりがちですが、敢えて選ぶとしたら誰かな……比較的新しいキャラクターの毒蛾くんかもしれません。夏木の言うところの「チューできない」体質というのがなんとも萌えですし、あの憂い顔がかわいい。毒蛾くんは珍しくというか、これだけキャラクターがいるなかで唯一かもしれないくらい「普通に美形」で、なんだかそこも不憫です、メタ的に不憫。そういうのが私は好きです。
そして、普段は男と男のコンビにしかときめかないはずの私が、心と能井や、ニカイドウとカイマン、ハルちゃんとカスカベ博士、などなど、男女のコンビについても一切まったく違和感なく「かわいい絆」として受け入れられるのもまた、ドロヘドロならではと言えるでしょう。逆に男と男の萌えというと「魔のオマケ」に出てきたシュエロンと喪六さんくらいかな……喪六さん(というか悪魔のみなさん)は見た目で性別が分かりづらいのでもしかしたら女性なのかもしれませんが。うーん、いや、やっぱりあそこだけはほもカップルであってほしい、私の偽らざる本音としてはそういう感じです。
なぜドロヘドロに限っては男女がオッケーなのかというと、これがまた、自分でもよく分かっていません。世界観のほうがいい意味で狂っていて(つまり現実世界からかけ離れているために現実を意識せずに済むので)既に居心地がいいからかもしれないし、女性の性格や体格がみな個性的で、つまり記号的な性的魅力から自由であるために嫌悪感を覚えにくいのか、まあそういうのの合わせ技なのかもしれませんが、嫌悪感を覚えないどころか、カイマン改め会川が「さよなら」と告げるシーンなどは乙女系コンテンツ(女性向け恋愛シミュレーション要素のあるコンテンツ)でもそうそう味わうことのできない心のときめきを得たので、作者の手腕には脱帽するほかないです。もう全裸でもいい。
あと、いっとき目からきのこがはえて弱っていたニカイドウには、女性キャラに対するものとしては異例かつ多大な萌えを感じました。あのような体験は初めてと言っても過言ではなかった、なので、私にとってドロヘドロはある意味理想的な「少女漫画」であると言えます。
キャラクターの魅力もさることながら、ストーリーもまたとっちらかっているようで一本筋が通っていて、寄り道しながらも壮大な謎がじょじょに解かれていく感じはそんじょそこらのミステリー以上というか。私はあまり先読みがうまくないのもあり、謎の片鱗が見えるたび毎回ハラハラして心踊ります。最新20巻の流れを見るに、そろそろ大詰めかもしれないですね。すべてが明らかになるとすれば楽しみですが、それ以上に終わってしまうのはさびしいので、複雑な気分です。
そしてさらに、絵の迫力がすごいというのも言っておかなければ気が済まない。人物の輪郭や背景における、何重にも描き込まれた太く力強い線と、キャラクターの目や口といった顔のパーツを描く繊細な線の対比。いわゆる絵画の技法を凌駕するパースの取り方、厚塗りの極地と言わんばかりに主線・枠線の外側まで色が置かれたカラーページ。これをオリジナリティを言わずして……というやつではないでしょうか。キャラクターやストーリーから切り離したとしても、林田球のイラストそのものが果てしないパワーを持っている。たとえ日本語が読めなかったとしても、目で絵を追いかけるだけでドロヘドロは楽しいと思う、憧れや尊敬を軽く通り越して作者は神なのかな、と思うレベルです。
いやもう……ドロヘドロについて語り出すと終わりそうにないので、一旦このへんで。
「ぢるぢる旅行記(総集編)」ねこぢる/「インドぢる」ねこぢるy

- 作者: ねこぢる
- 出版社/メーカー: 青林堂
- 発売日: 2001/04
- メディア: コミック
- 購入: 1人 クリック: 47回
- この商品を含むブログ (45件) を見る

- 作者: ねこぢるy
- 出版社/メーカー: 文春ネスコ
- 発売日: 2003/07
- メディア: 単行本
- 購入: 2人 クリック: 12回
- この商品を含むブログ (43件) を見る
本棚写真では「インドぢる」が抜けていますが、ちょうど写真を撮っていたとき読み返し中で机に置いてあったからで、普段は2冊くっつけて並べています。ねこぢるとねこぢるy。故人と元夫。ただ私には、彼らの生き方や彼ら自身についてそこまで深い思い入れがあるわけではありません。彼らの関係性は知っていたし、ねこぢる作品の総集編と「四丁目の夕日 (扶桑社文庫)」はそれぞれ持っていて何度も読み返している、今では山野一の最新作「そせじ(1)」も楽しく読んでいるけれども、ほぼそれだけ、そこまでで、つまり彼らの熱狂的なファンと言うには心もとない、けどそれでも、私はこの2冊の旅行記(?)については特別に好きでしょうがなく、何度でも読み返してしまうのです。
まあ私はもともと旅行記というか、旅エッセイは文章・漫画問わず好きで手当たり次第に読んでおり、なぜかというと自分が旅好きで放浪癖っぽいものがある、にも関わらず外に出るのは常に億劫ですぐお腹を壊すし眠くなるし人と会うと作悪吐くしの超インドア派だから、せめて人が旅している様子を見ていたい、ということで旅エッセイが好きなのですが、そういう自分の好みは置いておくとして、つまり「旅エッセイ」としてではなくても、「ぢるぢる旅行記」と「インドぢる」が好きということになる。
なんというか、私はやたらとこの頃の山野一の「文章」が好きで、「インドぢる」におけるダラダラとした語り口調はメロディもないのに邦楽のだるいロックみたいだし、そういうだるさのなかにときおり混入される心臓をえぐり込むような鋭い描写は本当に堪える、でも意図してやっているわけではなく、自然とそうなってしまうんだろうなという感じがして、もちろん山野一が生まれながらにしてなんの努力もしていないという意味では決してないですが、ああこの人は「天才」だなと思ったりする、で、その「インドぢる」をより深く味わうためには、ねこぢるの生前に描かれた「ぢるぢる旅行記」も読まなくちゃいけない、みたいな、前後関係がおかしいですけどそんなわけで、2冊セットで、単なる旅行記としてでもなく好きです。
あーいっぱい文章を書いているのに結局好きとしか言っていないぞ……弱ったなあ、「好き」を感覚抜きで説明するのは難しいです。ただ「好き」というよりは、大切な本、という感じもする。
たとえば私がいっとう好きなのは、山野一が書いた「ねこぢる旅行記」のあとがきの一文。何度も何度も読み返して覚えてしまっている文章がこれです。(※(略)部分は私が勝手に略しています、私の好きな一文には主語がなく、それだけでは意味が取りにくいと思うので)
迷路のような路地を歩く彼女は楽しげで、(略)
気候や疲労で顔はどんどんやつれていくのに、
目だけがきれいに澄んでいくのが印象的でした。
ねこぢるの感じたままに描かれたのであろうインド旅行記としての「ぢるぢる旅行記」も魅力的ですが、そのねこぢるを見守る山野一の視線の鋭さとやさしさがこの一文から余すことなく伝わってくる感じがして、ねこぢるは若くして死んでしまったけれども、かつて夫婦だったこの二人の生き方に憧れるというか、ある意味では「夫婦」について綴られたエッセイのようにも見えてくる、亡きねこぢるを偲ぶ意味合いも持つ「インドぢる」のほうが、その傾向は強いかもしれません。
そのうえ「インドぢる」のほうはとくに、生き残った側の切なさややるせなさが、インドというでたらめな土地のあまりの「濃さ」によって薄められていく感じがどこか爽快で、読んでいるほうにも伝染していたはずの悲哀がどんどん有耶無耶になっていく、不思議な読書体験でした。
また、「インドぢる」における好きな文章というとこのあたり。
市役所の職員かその下請けの人が時々やって来て、立ち木に水をまく。都会の緑地は大切にしなければならない。また別の職員かその下請けの人が時々やって来て、木の下の人たちの瞳孔をのぞく。瞳孔が収縮しない人はトラックで材木のように回収され、収縮する人はしなくなる日まで放置される。
(p.26、「路上生活者」より)
反復される単語のリズムと、「緑地は大切に」というアホみたいな標語のようなもの、一見悲惨な「瞳孔が収縮しない人」が見えるけれども、いつかすべての人間の瞳孔が収縮しなくなると思うと、なんだか全部どうでもよくなって、すごく気持ちがいい。これを読むともう、ベタベタした自意識まみれの純文学なんか読んでいられない、という気分になります。しばらくしたらまた自意識まみれの文も読みたくはなるんですが、はい。数時間か数日か、ちょっとだけすべてのしがらみから浮いたような気分になれるのは、やっぱりなかなかほかの本にはない感覚で、「インドぢる」と「ぢるぢる旅行記」はどちらもすごく好きで、そして、大切な二冊です。
「気分はもう戦争」矢作 俊彦、大友 克洋(全1巻)

- 作者: 矢作俊彦,大友克洋
- 出版社/メーカー: 双葉社
- 発売日: 1982/01/24
- メディア: コミック
- 購入: 2人 クリック: 32回
- この商品を含むブログ (84件) を見る
これはタイトルが好きというか、作中で間違って銃で撃っちゃって死んでる相手に「あっごめん」っていうノリとか、そういうのがおもしろいなと思う程度にしか分かってないのに手もとに残しているという、まあ大友克洋だしな……ということで、あんまりちゃんと紹介もできずすみません。Amazonレビューとか見ても、内容にきっちり触れているコメントはほぼないので、これを好きな人たちも雰囲気というか、このノリが好きで読んでいるのかな、と思います。
個人的な興味としては、「産業としての戦争」とか、SF的な世界観でよく使われる小道具である「民間軍事会社」とかが出てくる話が好きでよく読むし、自分でも二次創作のネタにしたりするので、資料のような意味合いもなきにしもあらず。
「凍りの掌 シベリア抑留記」おざわ ゆき(全1巻)

- 作者: おざわゆき
- 出版社/メーカー: 小池書院
- 発売日: 2012/06/23
- メディア: コミック
- 購入: 2人 クリック: 17回
- この商品を含むブログを見る
これを「気分はもう戦争」の隣に並べるのは全然よろしくないので移動させたいのですが、なんとなくこの並びになってしまっています。実際に起きた「戦争」について、作者の父の体験をもとに描かれた作品。それまで漫画作品ではほぼ見かけることのなかった「シベリア抑留」がテーマです。このテーマを漫画で分かりやすく読むことができるようになったというだけで、非常に意義のある作品ではないかと思います。
この漫画の主人公であるところの作者の実父は、「一度も実弾を撃つこともなく」終戦を迎えますが、そこが地獄の始まりだった……という話。終戦間際に出兵させられた若い兵士たちは、戦争が終わってもすぐには日本に帰ることができず、シベリアで捕虜のような扱いを受け、一年以上も過酷な労働を強いられます。作者おざわゆきの絵のタッチはやわらかく、どの兵士もみな幼くかわいらしい顔をしているように見えますが、その彼らがみるみる痩せこけ、弱って倒れていく様は、漫画という表現、しかもこのやわらかい絵で描かれるからこその凄みがあるようで、読んでいてひどくつらい気持ちになります。
ただ私がその「理解しやすい悲惨さ」以上に衝撃を受けたのは、それらの過酷な状況を生き延びて帰国したあとも、旧ソ連に長くとどめ置かれていたということから、「共産主義に洗脳されたのではないか」という疑いを受けつづけ、働き口もなかなか見つからなかった、という部分でした。主義思想の対立は、人類の発展においては避けて通ることのできないものだとは思いますが、帰還兵に対するこの扱いはまさにお国柄とでも言うべきか(GHQのそれこそ「洗脳」の効果でもあったのでしょうが)、現代のいじめの構図でもよくあるような「決めつけ」と「差別」のオンパレードで、語られているのは60年以上前の出来事であるのに、昨今の社会の有り様とそれほど変わりなく見えて、ずいぶん情けないような悲しい気持ちになりました。
読んでよかったと思った漫画ですし、折りに触れ読み返したいと思う漫画でもあります。私が持っているのはA5サイズ、やや大判のものですが、今は大きめコミックサイズのものが新装版として刊行されているようです。
「END&」鈴木 志保(全1巻)

- 作者: 鈴木志保
- 出版社/メーカー: WAVE出版
- 発売日: 2006/10/19
- メディア: コミック
- クリック: 21回
- この商品を含むブログ (29件) を見る
不思議な漫画です。いわゆるサブカル、サブカルのどまんなか。なぜ買ったのか覚えていないのですが、後半のカラーページ(フルカラーではなく青と赤の二色刷り)の美しさになんとなく惹かれつづけて今に至ります。それほど頻繁に読み返すわけではないですが、手放すのもなんとなく惜しいような、本棚の彩り的な位置づけで置いてある一冊。
絵柄・コマの演出は楠本まきに少し似ているかな……でもそこは楠本まきが絶対的な元祖というわけではなくて、この世代のこういう漫画を描く人たち(90年代前半に少年少女でも青年レディコミでもなく耽美・スタイリッシュ系を担っていた人たち)に共通している言語みたいな気もします。
作者があとがきで一切触れていないので違うとは思うのですが、「チルダイ」という短編に出てくる女性の名前が「キリエ」なのは、キリスト教の礼拝などで神に呼びかけるときに使われる「キリエ、エレイソン」の「キリエ」かなあと思ったりしました。なんかそういう言葉遊びみたいな読み方が好きです。
「監督不行届」安野 モヨコ(全1巻)

- 作者: 安野モヨコ
- 出版社/メーカー: 祥伝社
- 発売日: 2005/02/08
- メディア: コミック
- 購入: 7人 クリック: 370回
- この商品を含むブログ (721件) を見る
入眠前などにわりと軽めの漫画を読みたいな、というときにはそれほど深く考えずに読むことのできるエッセイ漫画を選ぶことが多く、これまで実に様々なエッセイ漫画を読んできた私ですが、そのなかでもとくに気に入っていて、且つ面白さ的にもダントツだなと思っているのが本書、安野モヨコが夫・庵野秀明との生活を描いた「監督不行届」です。
だいたいにして、私は安野モヨコのファンでもあるし、庵野秀明のファンでもある。となれば、この夫妻のエッセイなんて面白いに決まっているわけです。ただそういう色めがね抜きにしたって、「それほどオタクでもないけど根っこはオタク、でもオタクを隠しつつリア充に憧れながら生きてきたしっかり者のヨメ」と、「根っからのオタクでオタクを隠すことなく生きており、仕事はすごいけどそれ以外ではちょっと頼りないダンナ」のコンビが繰り広げる日常といったら、そりゃもう誰が読んでも面白い……はず。
だがしかし、私の本当の思い入れを語ろうと思ったらエヴァから……あの頃エヴァのパイロットたちとリアルに同い年だった自分の思い出から……始めたいところですが、それをすると何万字かかるんだみたいなことになるし、この漫画の内容とはてんで関係なくなるので思いっきりショートカットすると、安野モヨコの描く庵野カントク、簡略化された絵なのに特徴掴みまくっててすごい、めっちゃ似ててすごい、という感じになります。あと安野モヨコ自身を表すロンパースちゃん、「美人画報」のときからこのロンパースかわいいなーと思っているので、また会えて嬉しかったです。「美人画報」シリーズは文庫版で3冊とも揃えました。本来それほど美容には興味のない私が、安野モヨコの描くものなら興味を持って読めるのであれはそういう意味でもすごいエッセイでした。
と、例によって話が逸れていますが、本書「監督不行届」は、漫画エッセイ部分をすべて読んだあとに、庵野カントクサイドのインタビューが掲載されていて、それがまたいい、ということも付け加えておきます。愛にあふれている……あのエヴァをこの世に生み出した(生んでしまった)庵野カントクが、一人の女性への愛を、もしかしたら不器用かもしれないけど一生懸命な愛を語っている、それが読者にちゃんと伝わってくる……なんかもう感慨深くて、本編のエッセイはにこにこ笑いながら読めるのに最後はちょっと泣きそう。この素晴らしくお似合いでかわいらしい夫妻が、どうか末永く幸せでありますようにと、完全なる赤の他人ながら祈らずにはいられない私です。Wアンノに幸あれ……。
なお、昨年ミニアニメ化された際にはヨメ役を林原めぐみ、カントクくん役を山寺宏一が演じていて、やべえこれ以上ないほどぴったり、そしてさすが豪華、といった感想を持ちました。
(後半へつづく)